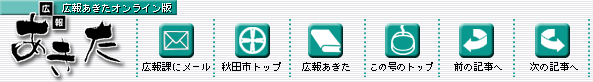|
|
| 2004年9月10日号 |
くぼた旧町名物語・まちの生い立ち
|
(5)家督のまち編
|
|
外町には、城下町の商業を統制するため秋田藩から特定の商品を独占販売する権利を与えられた「家督町」がありました。今は近所のスーパーマーケットで何でも買えますが、当時は“その町”でしか取り扱えない物があったのです。 |
|
外町の町割り※色字が家督町
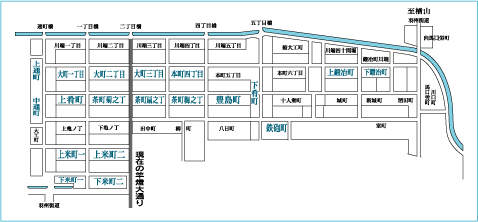 ■外町の家督町 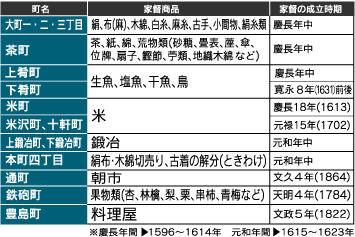 |
藩内の魚商品の流通もチェック |
|
慶長十七年(一六一二)に土崎から移ってきた上肴町は、土崎時代、すでに肴(魚)商売の家督を与えられていたとも伝えられ、外町に移ってからも、ほどなく家督を得たものと思われます。上肴町から南に四町隔て、同じく土崎から移り住んだ下肴町は、秋田藩に願って、寛永八年(一六三一)前後に、肴家督を取得。寛文十二年(一六七二)には、これまで一切禁止されていた鳥の販売も両町の家督に含まれるようになりました。 |
米小売の掟も定めた米町 |
|
上米町一丁目・二丁目、下米町一丁目・二丁目の四町は、慶長十八年(一六一三)、土崎の穀丁から移り住み、米家督を与えられました。 |
「鍛冶の町」「果物の町」も生まれる |
|
久保田城築城に奉仕した見返りとして家督が与えられたといわれる上・下鍛冶町。土崎に住む鍛冶職人十八軒が外町に移り、元和年間(一六一五〜一六二三)に鍛冶家督を得て、城下周囲三里(約十二?)にわたり農具などの鍛冶仕事を独占的に引き受けました。 |
城下町・御休み処 |
福祉のさきがけは町人たちの手で |
|
江戸時代を通じ幾度となく起きた凶作や飢饉が原因となり、久保田の町も、その日の暮らしが困難な人々が増えていきました。
このような状況を憂い、文政12年(1829)、外町の町人那波三郎右衛門祐生が、中谷久左衛門、塩屋善兵衛ら同志72人を募って、生活に窮する人々などを救済するため立ち上がりました。 これらの同志たちがお金を出し合い、知行地(武士に与えられた土地)を買い入れ、そこで取れる米などを豊作・凶作に関係なく備蓄し、その救済にあてようとする事業でした。これを聞いた秋田藩10代藩主佐竹義厚は大いに喜びこれを許可しました。 その後賛同する人が191人に増え、合計で2千両、銀十貫文となり、これをもって知行地230石(1石で取れる米の量が約150kg)ほどを買い入れ、ここに「感恩講」が発足しました。 文政14年(1831)には本町六丁目に感恩講の米などを保存する蔵2棟を建造。町奉行からも「藩の運営でもなく、私的なものでもなく、長きにわたって保てるように」と助言を受けました。これ以降、町奉行の監督の下で町人によって運営されていくことになり、折りにふれ救済の手をさしのべてきました。 秋田の社会福祉は町人たちによってその大きな一歩を踏み出したのです。 |
 |
Copyright (C) 2004秋田県秋田市(Akita City
, Akita , Japan) All Rights Reserved. webmaster@city.akita.akita.jp |