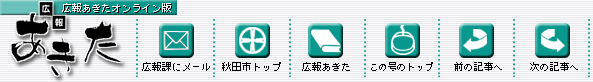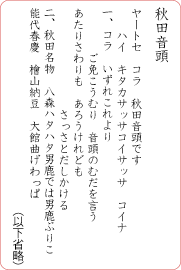|
秋田藩主佐竹氏の菩提寺である天徳寺には、十二代にわたる歴代藩主の肖像画が所蔵されています。
戦国時代を駆け抜けた初代義宣が甲冑姿、明治維新を迎えた最後の藩主十二代義堯が洋服姿ですが、そのほかの歴代藩主が皆、衣冠束帯の折り目正しい姿で描かれている中、一人だけ冠をかぶらず、右手に扇子を持ち、紋付き袴であぐらをかき、リラックスした姿で描かれてる殿様がいます。二代藩主義隆です。
義隆は、岩城家より初代義宣の養子となり、佐竹氏を継承しました。藩制の確立に努め、新田開発など藩内の産業発展にも尽くしたこの二代藩主には、秋田が全国に誇る有名な民謡・踊りに関わるエピソードが伝えられています。
質実・勇壮な踊り
秋田音頭の誕生
|
寛文三年(一六六三)、義隆は久保田城下に流行していた踊りを見ることになりました。殿様の前で踊りを披露するということで、城下の人たちが寺町にある鱗勝院で踊りの練習をしていたところ、ある者が、柔術の動きを取り入れた踊りを振り付けして、みんなに教えました。
後日、この踊りを見た義隆は、その質実・勇壮な動きにとても喜びました。義隆と城下の人たちの交流から生まれたこの踊り、これが現在の秋田音頭のもとになったとも伝えられています。
秋田音頭のルーツに関しては、上方の旅役者が伝えたという説、また外町(町人町)の芝居から生まれたという説など、様々な説・伝承があり、義隆に関する伝承も事実かどうかは、はっきりわかりません。しかし、天徳寺が所蔵する義隆の肖像画の表情は、秋田音頭誕生のエピソードのような、城下との楽しい交流もあったのではないかと思わせる柔和で楽しげなものです。秋田音頭の原型となった踊りを見て、久保田城下の文化、活気に触れ、満足しているような表情にも見えないでしょうか?
|
|