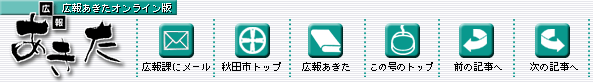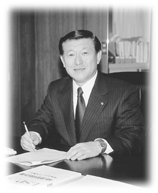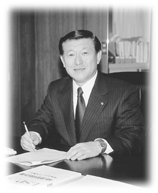
市長●佐竹敬久
|
今年も先月の土崎港曳山まつりに続き、今月三日から六日までの竿燈まつりで秋田の街がにぎわいました。
全国津々浦々、大小数え切れないほどの祭りがあり、その起源は多種多様ですが、古くからの祭りの多くは五穀豊穣を祈ることを目的としたもので、収穫を前にした夏から秋にかけて催されるものが多いようです。
いずれにせよ封建時代においては、いわゆる農民や町民など庶民にとっての数少ない出会いの場であり、楽しみの場であったものと思います。
時代が変わっても、祭りは老若男女、大きな楽しみの場であり、毎年きっちりと巡ってくる祭りのたびに、直接参加し汗をかく側の人も、見て楽しむ側の人も、各人各様に想いを新たにするのではないでしょうか。
しかし、多くの祭りを見てみますと、長い歴史を刻みながら持続されている祭りがある反面、すたれてしまい細々と行われている祭り、あるいは歴史として存在するだけの祭りなどがあります。 |
また現存する祭りにも、地域経済振興という視点から、集客に重きをおいた観光行事的色彩が濃くなったもの、あるいは少子化や共同体意識の変化のなかで形態を変えながら維持し続けているものなどがあります。
しかし、どの祭りにしても、誰しもが自らの地域の祭りこそ最高であると信じており、祭りには規模の大小や知名度などとは別の尺度の、その地域の人にしかわからない奥深いものが存在し、他地域の人があれこれ言う筋合いのものではありません。
また、近年の傾向として大規模な祭りの開催には、各種規制解除や広範囲なPR面などで、どうしても行政の一定のかかわりが必要になってきておりますが、祭りは自由度が命、行政参加は必要最小限が原則です。
結局なくなりましたが、ある祭りのように、参加者に行政が日当を支払わなければ成立しないような祭りは、そもそも存続意義はありません。
いずれにしても、祭りの本質は、直接参加者が祭りの意義を感じ、心意気を示せることにあります。 |
主人公はあくまで直接参加者、見物客は応援者、行政は側面支援者、この形が理想型ではないでしょうか。
少子化の中で、どこにこんなにいるのかと思わせるほどに若者が集まる港曳山まつり。若者やベテランの差し手、囃子方が見事な演技を見せる竿燈。様々な課題もありますが、秋田の二つの代表的な祭りは永遠にありたいものです。
「今年の港まつり、えがったな! んだども、竿燈も最高だったで!」 |

秋田の夏を熱くする竿燈まつり |
|