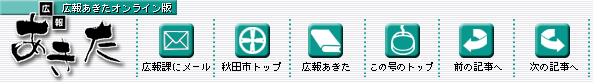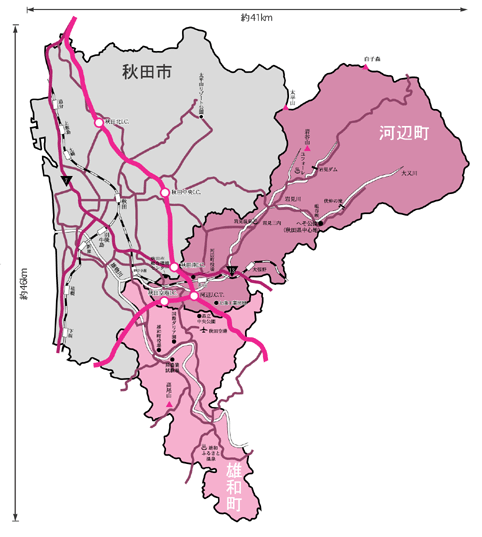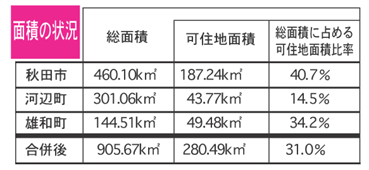|
|
| 2003年10月10日号 |
1市2町の歴史を読む |
せせらぎの町
|
||
|
輝く緑と水の里
|
||
|
建都400年の中核市
|
|
秋田市の開発は、千二百年あまり前にさかのぼり、天平五年(七三三)、大和朝廷が北辺守備の拠点として、高清水の丘に出羽柵(秋田城)を設置したことに始まります。 |
|
|
1市2町の面積の合計は905.67平方キロで、県の総面積の7.8%を占めます。 |
|
秋田市合併推進局 |
 |
Copyright (C) 2003秋田県秋田市(Akita City
, Akita , Japan) All Rights Reserved. webmaster@city.akita.akita.jp |