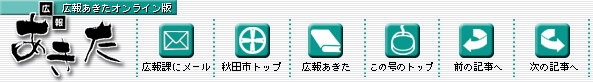市長●佐竹敬久
|
師走に入り今年も残り少なくなってきましたが、今回は私の小中学校時代を懐かしんでみることにします。
まず、冬が訪れる前の秋の恒例行事に全校あげての刈り取り後の田んぼでのイナゴ捕りがありました。
校務員さんに佃煮にしてもらい、昼のおかずに分けられましたが、今では高級珍味のイナゴの佃煮も当時は貴重な栄養源でした。
また、学校の薪ストーブの焚きつけになる杉葉拾いも欠かせない晩秋の学校行事でした。今では学校も家庭も暖房設備が完備し、およそ体が凍りつくような経験をすることは希ですが、当時は薪当番に当たれば吹雪の中を薪小屋まで薪束を取りに行かなければなりませんでした。
オンボロ校舎の教室の窓際には雪が吹き込み、机の上のノートが雪でにじむ光景も間々ありました。
そのような中では、皆がほっぺたや耳を霜焼けで真っ赤にしながら、あかぎれでかじかんだ手を摩って自ら暖まるのが自然な姿でした。 |
また、時々ゆるんだ煙突の継ぎ目から教室内に煙を吐き出す薪ストーブの上には、冷えた弁当を温めるための暖飯器が載っていました。それぞれ家で詰めてもらった各自の弁当を入れて温めているうちに、何となく教室の中には漬け物の蒸けたような香りが漂ってくるものでしたが、漬け物、梅干し程度が日常の弁当のおかずで、塩の効いたボダッコ(塩鮭)や卵焼き、当時出始めた魚肉ソーセージなどは上等の部類でした。
体育の時間は、零度以下に凍りついた木造の体育館の波の打った杉床の上や雪が積もったグラウンドを全身濡れながらも体から湯気が出るほど全力で走り回ったものです。満足な体育着・防寒着や雪靴などなくても不思議に風邪をひくことはなかったような気がします。
現代とはあまりにかけ離れた貧しく何も無い状況は、私の子どもに教えても想像もできず、聞きたくもないような顔をしていますが、ほんの三〜四十年前までどこにでも見られた光景で、一定の年代以上の皆さんは経験済みのことです。 |
進歩することは良いことですし、豊かになることは決して悪いことではないことは確かです。また、私たちの年代が経験した貧しかった思いを、これからの子どもたちにさせてはならないことも確かです。
しかし、ひとつひとつの良いこと、正しいことの単純な積み重ねが果たしてトータルとして良い結果につながるか否かは、後世の判断に委ねられることになるような気もします。 |

昭和30年代の給食風景 |
|