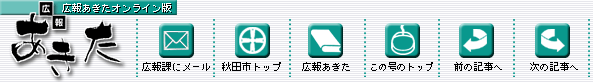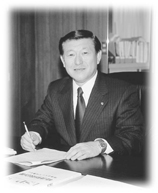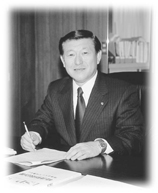
市長●佐竹敬久
|
今年は雪のない正月で、これまで幾度か寒波らしきものが襲来しましたが、その寒波も「根性」がなく今のところ秋田としては過ごしやすい日々が続いています。
しかし、もともと秋田の産業や暮らしの仕組みは、「冬は雪が降って寒いもの」という前提で形作られていますので、暖冬を一概に喜んでばかりはいられないようです。
本市のオーパススキー場もそうでしたが、年末年始の稼ぎ時に雪がないスキー場があったり、冬物衣料や灯油が売れないという声も聞かれ、はたまた秋田の食卓の定番「ガッコ」が旨く漬からず、すぐ酸っぱくなるなどということも耳にします。
この後、毎年暖冬ということであれば、それに合わせた商売の仕方や暮らし方にすることもできますが、傾向としてはひと冬ごとに少しずつ暖かくなっているように感じられるものの、誰も来年の冬を確実に推し量ることはできません。 |
さて、本県では小正月行事から発祥した地域色豊かな冬の「まつり」が各地で催されています。
勇壮な本市の三吉神社の梵天や大館のアメッコ市、男鹿のなまはげ柴灯まつり、横手のかまくら、湯沢の犬っこまつり、刈和野の大綱引き、六郷の竹打ち、さらには西木の紙風船上げ、それに角館の火振りかまくらなどが代表的なところでしょう。
また、地域の皆様のご努力により復活した仁井田の火振りかまくらや楢山のかまくら行事などもあります。
私も角館での少年時代には手ぬぐいで頬被りをして、燃えさかる俵の綱をギリギリまで持ち続け、眉や前髪を焦がした経験がありますが、子どもたちにとって冬の特色ある行事は何よりの楽しみだと思われます。
ところで、これらの行事には材料として、あるいは安全対策として雪があることを前提としたものが多く、中には雪が少ない年に中止を余儀なくされたものもあります。 |
加えて、今年で二十九回目となり大勢の人でにぎわった八橋運動公園での「童っ子の雪まつり」も雪があればこそのまつりですし、きりたんぽやしょっつるなどの郷土料理や秋田の銘酒も、雪景色の中で「ふうふう」言いながら味わうのが一番です。
一方で寒さや多雪を嫌いながら、他方ではそれらを前提とした社会構造があり、相矛盾した命題のはざまで暮らしていかなければならない私たちですが、できればお天道様からは寒さも雪も極端でなく、毎年「それなり」の冬を授けていただければと思いながら今年も立春を迎えました。 |

雪と炎の対比が美しい仁井田の火振りかまくら |
|