「人間は考える葦である」という有名な言葉があります。人間は水辺の葦のように弱い存在であるけれども、考えるという偉大な能力を持っている特別な生物、というような意味だそうです。
西暦千六百年代のフランスの哲学者であり、かつまた数学者、物理学者としても大きな功績のあった、ブレーズ・パスカルの言葉です。
天才ともいえるパスカルの功績の一例をあげますと、まず機械式計算機の開発があります。五十代後半より上の年代の人はお分かりと思いますが、四十年前ころまで使っていた、「チーン」という音を出す手回し計算機の原型ともいえるものです。
また誰もが中学時代には、液体の圧力の大原理として「パスカルの原理」を習ったはずですし、「ヘクト・パスカル」という気圧の単位は特に台風時の気象予報などでよく耳にしていると思います。 |
 4月16日、岩見三内保育所竣工式で
|
さて、ここでは何もパスカルの功績を紐解こうとするものではありません。「考える」という人間の尊厳ともいうべき特質が、最近危機にひんしているのではという私の心配事を少し述べたいと思います。
理由があっても許されることではありませんが、なぜいとも簡単に人を傷つけたり、殺めたりするのか。最近のマスコミをにぎわす悲惨な事件の連続には、憤りを通り越し最大限の怒りを覚えます。他人ばかりか結局は自分も台無しにしてしまうというごく当たり前の考えが少しも浮かばないのでしょうか。
凄惨な事件だけではありません。政治・行政の世界でも経済の世界でも、ちょっと考えて動けば、こんなおかしなことになって多くの人を悩ますことにはならずに済んだのに、という事があちこちで見受けられます。
はたまた、状況・内容を考察せずに、一方的な批判や思い込み論を振り回して辺りを惑わすなど、「もう少しお考えになってから口にした方がよろしいのでは」という場面に出くわすことも間々あります。 |
加えて、最近なんでもかんでも「改革」ばやりですが、言葉とは裏腹にいったい何が改革なのか疑問を抱かざるを得ないことが多く、しっかりと考えを巡らし、うかつにだまされないようにする必要があります。
情報化時代に特に大切なことは、押し寄せるさまざまな情報をうのみにせず、十分な思考を働かせ分析・評価したうえで自分としての情報に置き換えることにあります。
「考える」という人間の貴重な能力をもっと大切にしたいものです。 |
 よく考える−。
大人になっても忘れない
|

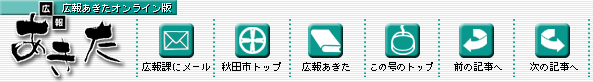
 4月16日、岩見三内保育所竣工式で
4月16日、岩見三内保育所竣工式で よく考える−。
よく考える−。