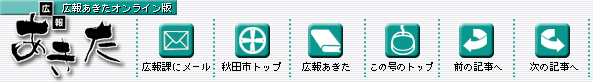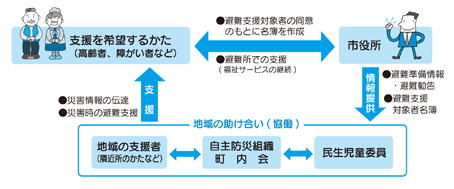|
|
|
※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
|
|
2010年4月16日号
|
災害時に備えた支え合いの地域づくり |
地域のみんなで手を取り合って |
|
災害時には「自らの身の安全は自らが守る。自らの地域は自らで守る」が基本です。でも、お年寄りや障がいがあるかたなど、災害の情報を得たり、避難したりするのに助けを必要とする人たちもいます。
ふだんから、いざというときに助け合える関係をつくっておきましょう。 市では、災害時に高齢者や障がい者などが安全に避難できるよう、「災害時要援護者の避難支援プラン」を策定しました。今年度から、この計画に基づき、地域で支え合う避難支援体制づくりを進めます。 |
地域でできることから取り組みを! |
|
まずは、地域のみなさんで想定される災害や避難方法などを話し合い、災害に備えておくことが大切です。
1 福祉災害マップの作成 支援が必要なお宅や避難所などを地図に記入し、避難経路や一時的な避難場所を確認しましょう。 2 地域みんなで防災・避難訓練 炊き出し訓練を行ったり、福祉災害マップをもとに、避難所まで実際に歩いてみたりしましょう。 3 いざというときの連絡網を整備 災害時に支援が必要なかたへ避難情報を伝える連絡網を整備しましょう。 4 個人ごとの避難支援計画 支援が必要な一人ひとりの個別の避難支援計画を作成しましょう。 ※今年度はモデル地区(3地区)で、地域で支え合う避難支援体制づくりに取り組んでいきます。 |
|
|
避難支援が必要なかたは名簿に登録を! |
|
災害時に家族だけでは避難することができない、または家族などの支援を受けられない状況にあるかたを市が作成する避難支援対象者名簿に登録します。
平成16年度から「介助支援対象者」として市に登録されているかたは、引き続き避難支援対象者として名簿に登録します。新たな対象者のかたには5月に市から案内を郵送します。 ■避難支援対象者 在宅で生活をしていて次のいずれかに該当するかた (1)介護保険の要介護1以上のかた (2)高齢者でひとり暮らし、高齢者のみの世帯、日中は家族が不在など (3)肢体不自由(1〜2級)、聴覚障害・平衡機能障害(1〜3級)、視覚障害(1〜3級)の身体障害者手帳をお持ちのかた (4)療育手帳Aをお持ちのかた (5)難病患者で特定疾患医療受給者証をお持ちのかた (6)小児慢性特定疾患の重症認定患者 (7)精神保健福祉手帳(1級)をお持ちのかた ※外国人や妊産婦、乳幼児がいる家庭などで避難支援が必要なかたも登録できます。名簿に登録を希望するかたは地域福祉推進室へご連絡ください。tel(866)2090 個人情報の提供に同意されたかたの名簿を地域の自主防災組織、町内会、民生委員と共有し、災害時には地域で避難を支援します。 ●問い合わせ 福祉総務課地域福祉推進室 tel(866)2090 ファクス(866)2417 |
声掛けで広げる地域のつながり |
|
大住地区自主防災連絡協議会
会長・長谷部三夫さん 大住地区では、地震や火事のほか、雄物川の堤防が決壊した場合の水害も想定されます。 地区内には高齢者が多く、その避難が最優先課題です。各町内で自主防災組織を結成し備えていますが、若い人が仕事などで家にいない日中の体制には心配なところもあります。 高齢者には地区全体で積極的に声掛けをしていきたいと考えています。最近は一軒家であっても隣近所の行き来がない家もありますし、まずは顔を覚えてもらわないと。地域のみなさんに協力をお願いして、いざというときにだれかが手助けできるように備えておきたいです。 |
自主防災組織をつくりましょう |
|
「自主防災組織」は、近所の人たちと協力し合い、地域の防災活動を効果的に行うための組織です。秋田市では現在654の町内会で組織が結成され、防災訓練や防災資機材の整備などを行い、災害時に備えています。
市では防災資機材の助成を行ったり、町内会などが開催する研修会や訓練に職員を派遣したりして活動を支援しています。 組織の結成や活動については防災安全対策課へご相談ください。 tel(866)2021 |
防災ネットで手軽に災害情報! |
||
|
 |
Copyright (C) 2010秋田県秋田市(Akita City , Akita , Japan)
All Rights Reserved. webmaster@city.akita.akita.jp |