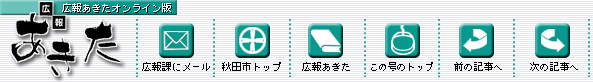|
2月は「福は内、鬼は外」、節分の豆まきで始まります。節分とは「季節を分けること」を意味し、特に、新年にあたる立春の前日を指すようです。季節の変わり目には、邪気が入りやすいと考えられており、鬼に豆をぶつけて邪気を払い福を呼び込むためとされ、豆をまくのは、その年の干支にあたる年男・年女や世帯主というのが一般的です。
県内の鬼と言えば男鹿のなまはげがあまりにも有名ですが、秋田市内でも、雄和の寺沢や下黒瀬などの各地域、そして下浜、豊岩地区などでやまはげが健在です。小正月行事として集落の家々を巡っては、一年の無病息災や五穀豊穣を祈願します。お面の素材が稲わらや木彫りだったりと、各地区ごとに特徴はあるものの、わら装束の「けら」をまとうなどの共通する部分も多く、「泣ぐ子はいねがー」「言うごど聞がね子はいねがー」「ウォー、ウォー」といった声は迫力満点で、小さな子どもたちには効果てきめんです。
こういった行事には、準備のための作業や終えてからの慰労会なども付きものです。そういった場では、互いの近況や子育てのことを語り合うなど、行事が地域の貴重な交流機会にもなっているようです。私としても、このような地域の暮らしや風土に根ざした風習は、春を待つ季節感や、健康・豊作を願う心が表れたその土地の大切な財産だと考えています。
|