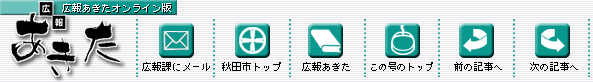|
さてこの春、時を同じくして、寺内地区では「秋田城跡歴史資料館」がオープンしました。ここに行けば、今からさかのぼること約1千300年、奈良時代の天平5年に高清水岡に置かれた、古代、日本最北となる地方の役所・秋田城のことや、そこでの役人の仕事ぶりなどがよくわかります。
史跡からは貴重な文字資料が多数出土しています。一つは漆紙文書で、たまたま役所の使用済み文書が漆容器の蓋として再利用され、漆によりコーティングされたことから、1千年以上もの間、腐らずに保存されていたことになります。他にも、木の札に文字が書かれた木簡なども展示されています。これらの文字は肉眼だとなかなかわからないことが多いのですが、資料館では、来館者が赤外線カメラで漆紙から文字が浮き上がる様子を見ることができます。これは、日本で唯一この施設だけでできる貴重な体験です。
その文字を読み解くと、「役人が山形方面に出張した折、用務を確認するために、象潟から秋田城に出した書状」や「習字の練習帳」と思われるものなどがあり、市役所職員の大先輩の仕事ぶりや古代地方行政の実体などが垣間見えてきます。
また、漆紙文書の「戸籍」を読み解いていくと、戸主の弟とその妻の姓が違っており、当時の家族制度が夫婦別姓であった可能性もあることなどは、とても興味深いところです。
他にも、天災や火災からの復興などを目的に、秋田城の建物が200年の間に6回ほど建て替えられていたことが、発掘や歴史書の記録からわかっています。当時の人びとがおそらく建て替えのたびに「新庁舎」と呼んでいたことなどを想像すると、いつの世も変わらぬ人間社会の姿をみるようでちょっと不思議な気分になります。
この資料館には、他にも和同開珎銀銭やまじないの道具などが多数、展示されています。また、資料館を含む秋田城跡史跡公園には、中国大陸渤海国との交流を裏付ける水洗トイレ遺構や東門などが復元されており、想像力をかきたてられる歴史ロマンがあふれています。
さわやかな初夏の風を受けながら周辺の散策も兼ねて、ぜひ一度足を運んでみてください。
|