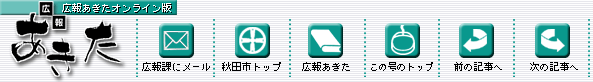
|
※掲載している情報は「広報あきた」発行当時のものです。
|
|
2023年1月6日号
|
新春市長コラム |
|
|||
2023年 飛躍
|
|||
 |
| 明けましておめでとうございます。本年がみなさまにとって、心穏やかで健やかな一年となることを心からお祈り申し上げます。 |
月うさぎに思うコロナ禍の日常 |
|
今年は卯年。幼い頃に「月で兎(うさぎ)が餅つきをしている」と聞いて、見上げた月には杵(きね)を持った兎の姿が…。きっと多くのかたにも経験があるかと思います。この月に暮らす兎の話は、利他の心を伝える仏教説話「天にのぼった月うさぎ」の伝説として諸国で語り継がれているそうです。兎にはどこか臆病な印象がありますが、感受性がとても豊かで、飼い主が落ち込んでいるとそっと寄り添ってくると聞きます。こうした相手を思いやる優しさと穏やかで美しい心は、長くコロナ禍を過ごす我々の日常にこそ必要なのだと思います。
新たな気持ちで迎えた年始めの夜。透き通った空気を吸い込みながら、誠実で心優しい「月うさぎ」に思いをはせてみてはいかがでしょうか。 *利他の心=自分のことよりも他の人を大切に思うこと |
ワールドカップの熱気と若者の未来 |
|
昨年末のサッカーワールドカップ(W杯)カタール大会では、日本代表サムライブルーの激闘に日本中が大いに盛り上がりました。特に印象深いのは、グループリーグ第3戦のスペイン戦です。「三笘(みとま)の1ミリ」と呼ばれた三笘薫選手の折り返しを、小学校時代からのチームメイト田中碧選手が押し込み決勝ゴール。試合後の熱い抱擁シーンは友情と信頼の笑顔に溢れ、切磋琢磨しながら挑戦の日々を過ごしてきた二人に、心から「ブラボー!」の賛辞を送りたいと思います。
スポーツと言えば、秋田の高校生も負けてはいません。年末年始の高校スポーツの全国大会では毎年多くの感動をもらっています。また、昨年は個人種目で素晴らしい活躍がありました。秋田商業高校3年の佐藤杏樹選手(レスリング)は、初めて参加した国際大会U17世界選手権で見事金メダルを獲得。秋田工業高校3年の大野聖登選手(陸上)は、秋田県勢としては実に43年ぶりにインターハイの2冠王者(800メートル、1,500メートル)に輝きました。また、秋田北高校1年髙橋凛選手(水泳)は、インターハイこそ僅差で表彰台を逃しましたが、レースのたびに秋田県の記録を更新している注目のスイマーです。 気心の知れた仲間と共に、秋田からトップをめざそうとする高校生たち。「秋田を盛り上げたい」という郷土への思いが頼もしく、応援にも熱が入ります。スポーツに限らず、若者たちが自らの将来に向かって挑戦できる土壌を作ることは我々大人の役割ですし、私は秋田市が「若者が未来を思い描けるまち」でありたいと思っています。このことは、若者にとって魅力あるまちの土台であり、地域への誇りと愛着の源泉だと信じています。 |
リスクの先に見えたまちの希望 |
|
さて、昨年11月、国連は世界人口が80億人を突破したと発表しました。ちょうど私が高校生だった1974年に40億人に達したとされているので、この50年足らずで人口が2倍に増えた計算となります。さらに2037年には90億人、2058年には100億人に達し、2080年代に104億人でピークを迎えるとの見通しがあるほか、今年中にはインドが中国を追い抜き、世界で最も人口が多い国になるそうです。
日本は2008年をピークに人口の減少局面に転じているので、なかなか実感が沸きませんが、地球規模の視点で考えると、先進国での人口減少、途上国での人口急増、まったく正反対の二つの変化が同時に起きています。 国連のグテーレス事務総長が「持てる者と持たざる者の間で大きな格差を解消しなければ、緊張と不安、危機と紛争に満ちた80億人超の世界に身を置くことになる」と警告するように、現代を生きる私たちには、経済的な格差の拡大、食糧・エネルギー問題、気候変動による自然災害といったリスクに向き合いながら、新しいパラダイム(物の見方や捉え方)への展開を図ることが求められています。 リスクを前にした時は「苦しい時こそ上り坂」の心意気を持って、縮こまることなく、前を向いて思考を切り替えることが必要です。時代の大転換点に直面している今、私たちは、改めて明日への希望を持ち、強く覚悟を決め、ピンチをチャンスに変えていくべく行動しなければなりません。 昨年は、竿燈まつりや土崎港曳山まつりを関係各位のご尽力のもと、3年ぶりに開催することができました。 …感染リスクを最小限にすること …伝統文化を次世代に継承すること …市民の心に未来を照らす火を灯すこと 様々な思いが巡り葛藤がありましたが、祭りの熱気がもたらすまちの一体感や会場に溢(あふ)れる若者たちの笑顔など、コロナ前まで当たり前と思っていた景色の中に希望があることを再認識しました。 リスクの語源はラテン語で「勇気をもって試みる」。将来への希望とリスクは常に隣り合わせですが、リスクをしっかりと受け止めて、恐れずに挑戦することが大切だと思います。 |
写真で振り返る2022 |
||
|
美術大学があるまち |
記念ロゴマーク 今年は秋田公立美術大学が開学から10年となる節目の年を迎えます。 2009年、私は公約の一つに「秋田公立美術工芸短期大学の4年制大学への移行」を掲げ、秋田市長に初当選しました。 2012年の同大学の設置認可の際には、文部科学省の姿勢が問われる事態となり、その過程が連日のニュースで大きく報じられました。「時代が求める多様な人材を育成・輩出する大学こそ、多様で自由な存在でなければならない」との覚悟をもって、国を相手に奔走した日々が昨日のことのように思い出されます。 そして「秋田公立美術大学」として初めてとなる入学式では、「新しい芸術的価値やデザインを生み出す力、地域における芸術創造を担う力、多様な価値観を交換・共有する能力を持ってグローバルに活躍できる力を育(はぐく)んでほしい」との期待を述べました。 美大は、この地に暮らす我々が認識していないまちの個性や価値を見出し、気づかせてくれる存在だと思います。これまでも美大と連携しながら、秋田駅周辺の市街地木質化や西口駅前広場(芝生広場)の整備、文化創造館などでの多彩な市民向けワークショップ、新屋地区における空き家の利活用、大森山アートプロジェクトなどに取り組んできました。 美大がまちのポテンシャルを引き上げてくれる一方で、この秋田という土地は、アーティストやクリエーターたちの感性を刺激する可能性に満ちたフィールドであるとも感じています。 このように相互補完的に地域資源が耕されることで、新しい文化が創造されるのだと思っています。また、県内各地の自治体において、教員や学生との協働プロジェクトが展開されている現状は、開学時に描いた「まちづくりに貢献し、地域社会とともに歩む」大学の姿が具現化していて心強く感じています。これからも「美術大学があるまち」のアドバンテージを最大限に生かしていきたいと思います。  秋田公立美術大学 |
写真で振り返る2022 |
||||
|
デジタル化を考える |
| 政府が進める「デジタル田園都市国家構想」は地方創生につながる取り組みの一つです。私は、これからのデジタル化を考えることは、視点を変えてみると、人間にしかできないことを考えることなのではないか、と思っています。 外旭川のまちづくりモデル地区では、「人口減少下にあっても持続可能な社会基盤の構築」と「交流人口の拡大による新しい活力や魅力づくり」の二つの目的を実現するため、先端技術を活用した次世代型農業の推進や、今後の成長が見込まれる洋上風力発電など、再生可能エネルギーを活用したゼロカーボン地区の実現、そしてデータセンターの誘致にも鋭意取り組んでいきたいと考えています。 こうした「未来が見えるまちづくり」の前提として、AI(人工知能)には代替できない人間本来の能力を見つめ直すことが大事です。人間が持つ強みとは、「協調…相手の感情や気持ちをくみ取って、コミュニケーションをとること」と、「創造…創造力を発揮して、ゼロから新しい価値を生み出すこと」の二つだと考えます。人間はいつの時代も、「協調」と「創造」の力を発揮することで、幾多の危機を乗り越えながら日々の暮らしを築いてきました。 こうした視点は、市政の基本理念、「ともにつくり ともにいきる 人・まち・くらし」に込めた思いとも重なり、そして、これからの社会のあり方を展望する際の重要なキーワードであると思います。 ◆ 46億年前に誕生した地球は、80億人という人口を抱えるまでになりました。国連が「80億という数字に目を奪われるのではなく、社会の変化に影響を受ける人々に手を差し伸べなければならない」と呼びかけるとおり、一人ひとりの生活の質を高め、心を満たし、新たな生きがいに出会える未来を創造することが大切です。30万市民を預かる私としても、市民一人ひとりが「元気と豊かさ」を実感できる活力あるまちづくりに全力を尽くしてまいります。「跳ねる」のが得意な兎にあやかって、コロナ禍を乗り越えて、ともに未来に向かって力強く飛躍し向上させる一年としましょう。 本年もどうぞよろしくお願いいたします。  バスなどタッチで支払い♪AkiCAがスタート!  建設の進む洋上風力発電(秋田港) |
 |







