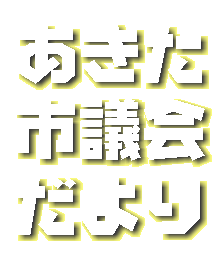
2002年4月26日 №106
平成14年2月市議会定例会から
最終更新 2002.6.18
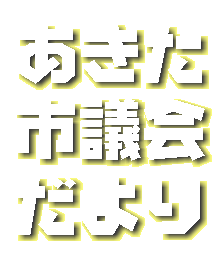 2002年4月26日 №106 平成14年2月市議会定例会から |
|
BSE(牛海綿状脳症)は、昨年9月の国内での感染確認以来、日本の畜産と関連産業及び消費者に深刻な影響を与えてきた。これは1996年のWTOの「牛に対する肉骨粉などの禁止勧告」に対する政府の対応が後手後手に回り、一層被害を拡大したからである。
今、畜産業界は、国民の牛肉に対する風評による不信と価格の大暴落で壊滅的状態にあり、早急な救済対策が望まれている。小泉総理は2月13日の衆議院予算委員会で国の責任を初めて認め、「どういう有効な手だてがあるか検討中」と答えている。
以上のような経過から、国はBSEの発生による混乱と経済的損害に対して、責任を持って万全の対策を行うべきであり、国民の健康を守り、食品の安全性の確保に努めなければならない。
よって、国においては、下記の対策をとるよう強く要請するものである。
記
1 安全な牛肉を安定的に供給する体制を確立するために、畜産農家に対して暴落以前の価格まで差額を補償することを基本とした対策に全力を尽くすとともに、流通、加工及び販売業者に対しても万全の対策を講ずること。
2 現状での一時的なBSE関連つなぎ資金や緊急対策事業資金では有効な対応策とは言えず、再建のための補助制度と利子補給を加味した長期的に返済可能な融資制度を創設すること。
3 肉用牛の出荷調整により出荷が進まないことに加え、廃用牛処理も進まず、これらへの対策の遅れにより、飼料代等の農家負担の増大や、BSE発生の不安が払拭されないことが指摘されていることから、早急に的確な現場対応に努めること。
先般、雪印食品がBSE(牛海綿状脳症)関連対策の一つである国産牛肉買い上げ制度を悪用し、外国産の牛肉等を国産牛肉と偽って、これを買い取らせたという極めて悪質な事件が発生し、雪印食品は、農林水産省からの詐欺容疑での刑事告発を受け、警察当局による一斉捜索を受けるに至っている。この事件に端を発し、他の食品会社においても、牛肉のみならず、豚肉、鶏肉、野菜等、他の食品について虚偽表示が行われていた実態が明らかになってきている。
これらの事件は、ややおさまりつつあったBSEに伴う国民の牛肉不信を再び惹起させたばかりか、国民・消費者の食品表示制度全般に対する不信を増大させたものである。その意味で、まずこれらの事件に対する徹底的な解明を進めるとともに、その情報公開と厳然たる措置を取ることを求めるものである。
また、これらの事件に関連し、「食品表示に全く信頼が置けなくなった」と現在の食品表示制度に対し、あからさまな不信感を表す消費者もおり、国産牛肉買い上げ制度におけるチェックを、より一層厳重にするとともに、現在の食品表示制度のあり方を抜本的に見直す必要がある。
食品表示制度が不十分であるならば、国民・消費者に正しい情報が伝わらないだけでなく、国民の健康と生命にかかわる重大事を起こしかねない。
よって、国においては、下記の事項に関して速やかに対応するよう強く要請するものである。
記
1 国産牛肉買い上げ制度による保管中の牛肉について不正がないか徹底解明することはもとより、他の食品についても表示に虚偽がないか総点検を行うこと。
2 JAS法や食品衛生法等の関係法における食品表示制度の抜本的見直しを行い、名称、原材料名、内容量、賞味期限、製造・輸入業者名及び生産地等のより詳細な表示を行わせ、その内容のチェック等、監視制度の強化・充実を図るとともに、違反者への罰則を強化すること。
近年、小児救急医療体制の不備から、小児救急患者の医療施設たらい回しや患者輸送の手遅れから重大な事態に至るなどの問題が全国各地で発生している。
小児科医そのものの数は近年横ばい状況であるものの、開業医の高齢化等に伴う診療施設の閉鎖や、ビル診療所等の増加などから、特に休日や夜間の小児救急医療体制の不備がクローズアップされ、大きな社会問題となっている。
また、患者・保護者の専門医指向等による小児救急患者の大病院集中と、共働き世帯の増加に伴う休日・夜間診療ニーズの激増が大病院小児科医等の激務と過労を招くとともに、それらがさらに小児科医志向の抑制に一層の拍車をかけていることが指摘されている。
こうした事態に対し、厚生労働省は、平成11年度から3カ年計画で、全国360地域の第2次医療圏ごとに、365日、24時間体制でいつでも子供を診察することができる小児専門救急医療体制の整備を目指した「小児救急医療支援事業」をスタートさせたが、平成12年度時点での実施地域は18県51地域(全体の14%)であり、平成13年12月末時点でも25県100地域であり、全体の27.7%にすぎない。その最大の要因が全国各地における小児科医の大幅な不足であり、各都道府県における小児救急医療の体制整備を極めて困難にしている。
よって、国においては、以上の現状にかんがみ、これまでの小児救急医療体制のあり方を抜本的に見直し、下記の事項について早急に実現するよう強く要請するものである。
記
1 小児救急医療及び小児医療にかかわる社会保険診療報酬の引き上げを図ること。
2 第2次医療圏(平均人口35万人)に最低1カ所ずつ、24時間対応小児専門救急医療体制が確立されるよう早期整備を進めること。そのため「小児救急医療支援事業」の抜本的見直しと充実・強化を図るとともに、国の助成を強化すること。
3 都道府県における小児医療の中心センターとしての中核的小児医療機関の整備を計画的に行うこと。
4 大学医学部における小児専門医の養成と臨床研修の充実を図ること。
|
|
|
|
|
|
![]() 一般質問
一般質問
- 鈴木 嘉重 (政秋会)
- (仮称)拠点センター
- 中心市街地再開発事業
- 平成19年秋田国体に向けてのスポーツ振興
- シビックセンター構想
- 医療
- 建築確認にかかる手続き
- 除排雪
- 河川改修
- 菅原 弘夫 (市民クラブ)
- 市長の政治姿勢
- 政策の企画立案
- 経済対策
- 秋田港コンテナ船の増加に伴う特別とん譲与税
- 入札
- 環境問題
- 家庭用生ごみ処理機の購入に対する助成
- 農業問題
- 介護保険制度
- 国民健康保険
- 病院の院内感染等
- 教育問題
- 本市のまちなみ
- 市営住宅
- 南部地域の諸問題
- 宇佐美 洋二朗 (社会・市民連合)
- 市長の公約と政治姿勢
- 平和行政
- (仮称)中央地域シビックセンター
- (仮称)芸術文化ホールの見直しと中央街区の再開発
- 救急救命士による気管内挿管
- 町内会館の運営費
- 秋田港周辺
- 秋田城史跡公園の整備事業
- 八橋運動公園整備事業
- 佐々木 勇進 (日本共産党秋田市議会議員団)
- 市長の政治姿勢
- 第5次秋田市総合都市計画
- 商業
- 教育
- ひきこもり
- 農業
- 障害者のためのバリアフリー化
- 榎 清 (政秋会)
- 市長の政治姿勢
- 農林業施策
- 淡路 定明 (市民クラブ)
- 土地利用計画と都市計画の推進
- 市街地の開発整備
- 交通体系の整備
- 創業の促進と既存企業の支援
- 住宅環境の整備
- 佐々木 晃二 (政秋会)
- 市長の政治姿勢
- 行政改革
- 日赤・婦人会館跡地の再開発事業
- 本市と関連のある業界団体への市職員OBの再就職
- 院内感染及び感染症
- 秋田港本港地区周辺の問題
議案以外の市政全般にわたり、会派を代表して6人の議員が質問しました。
主な質問と答弁の要旨を掲載しています。
小西 謙三議員 |
小西 謙三議員 |
相場 金二議員 |
相場 金二議員 |
塚田 勇議員 |
塚田 勇議員 |
藤田 正義議員 |
藤田 正義議員 |
加賀屋 千鶴子議員 |
加賀屋 千鶴子議員 |
成沢 淳子議員 |
成沢 淳子議員 |
議案以外の市政全般にわたり、7人の議員が質問しました。
主な質問と答弁の要旨を掲載しています。
鈴木 嘉重議員 |
鈴木 嘉重議員 |
菅原 弘夫議員 |
菅原 弘夫議員 |
宇佐美 洋二朗議員 |
宇佐美 洋二朗議員 |
佐々木 勇進議員 |
佐々木 勇進議員 |
榎 清議員 |
榎 清議員 |
淡路 定明議員 |
淡路 定明議員 |
佐々木 晃二議員 |
新行政改革大綱の見直しについては、大綱策定時に比較すると、国の構造改革や地方分権の進展により社会経済情勢が大きく変動していることや、13年度末に大綱に掲げた実施項目の約7割を達成していることから、更なる時代の要請に適応した市民に身近な市政の執行体制を構築するため、14年度において見直しを行います。 |
佐々木 晃二議員 |
退職後の関連団体への就職については、基本的に各個人の判断によって行われており、画一的に認めないことは難しいものと考えます。しかし、市民の疑惑を招くような事態は当然避けるべきであり、市民の公共工事発注システムに対する信頼性を確保するため、状況に応じては職員個人に対し、新たな判断を求めるなど適正な対応に努めます。 |
2月定例会の各常任委員会で交わされた質疑応答の中から、主なものを掲載しています。
![]() :請願
:請願
![]() :陳情
:陳情